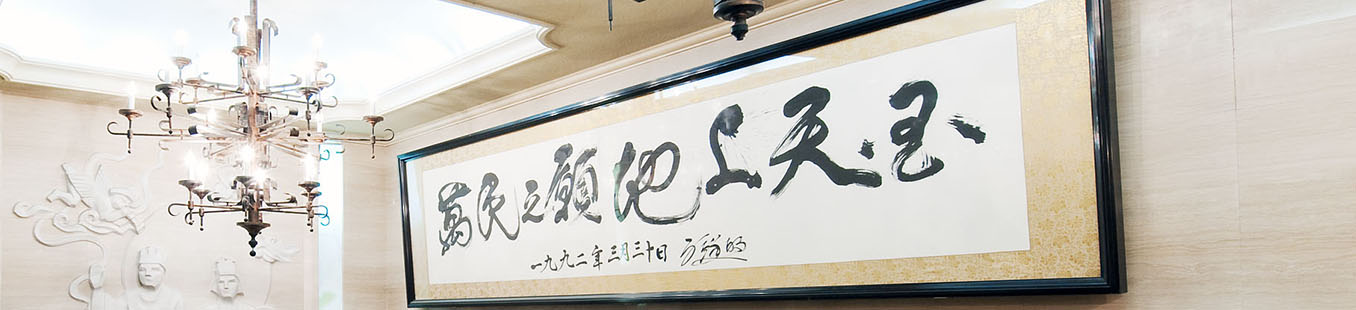ニュース
NEWS国連の人権専門家が東京地裁の解散命令決定に懸念を表明
プレスリリース
世界平和統一家庭連合
広報渉外局
今年10月1日付で、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)はプレスリリースを発出し、日本における宗教的少数派に対する人権侵害を憂慮する国連専門家4名の意見を発表しました。同専門家らは、学校教育の場で宗教を特別視することが、却ってスティグマ化による差別に繋がると危惧を表明すると同時に、今年3月25日に東京地裁が当法人に対して下した解散命令決定についても、国際法違反との警告を発しました。
以下、解散命令決定に関する専門家らの意見について解説します。
国連専門家4名は、解散命令の根拠とされた不法行為判決が、『社会的相当性』の違反に基づいており、それが『公共の福祉』に対する重大な害悪を構成すると東京地裁が判断したことを問題視し、「国際人権委員会が以前に指摘したとおり、『公共の福祉』という概念は曖昧かつ無限定であり、自由権規約(ICCPR)の許容範囲を超える制限を認める恐れがある」と警告しました。
国際自由権規約18条3項は、法律によって明確化されていない「社会的相当性」や「公共の福祉」といった概念によって信教の自由を制約することを禁止しています。ところが、過去に当法人に対して下された不法行為判決は、いずれも「社会的相当性」の逸脱といった曖昧な概念に基づいて違法性を認定していました。しかし、その結果、信教の自由を制約する結果をもたらしたことから、いずれも国際法違反となります。
また、「公共の福祉」に関して言えば、国際人権委員会はこれまで日本政府に対して「公共の福祉」によって信教の自由を制約しないよう繰り返し警告してきました。ところが、文科省はこれを無視し、「公共の福祉」の侵害を理由に当法人に対する解散命令を申し立てたのでした。本来このような申立ては却下されるべきでしたが、東京地裁はこの主張を認めて解散命令決定を下してしまいました。
したがって、今回の東京地裁決定は、過去に当法人に対して国際法に違反して下された判決を元に、「公共の福祉」の侵害を認定した、という点で、二重の意味で国際法違反であるといえます。
本来国連は、「司法の独立」への配慮から、司法に関する言及には慎重姿勢を採ります。まして、特定の国家の下級審決定に言及するなど、例を見ません。
本プレスリリースは、東京地裁決定の著しい国際法違反に鑑み、同決定が維持されることがあってはならないとの考慮により、この時期に発出されたものと考えられます。日本は自由権規約締約国である以上、こうした国連専門家らの警告を無視することは通常許されません。
なお、本プレスリリースが言及する国連専門家らとは、国連人権理事会から委託を受けた以下の4名の特別報告者らです。
•ナジラ・ガネア(Nazila Ghanea):信教または信念の自由に関する特別報告者
•ニコラ・ルヴラ(Nicolas Levrat):少数者問題に関する特別報告者
•ファリーダ・シャヒード(Farida Shaheed):教育を受ける権利に関する特別報告者
•ジーナ・ロメロ(Gina Romero):平和的集会及び結社の自由に関する権利に関する特別報告者
関連リンク(外部サイト)
OHCHR Japan: UN experts concerned by continued stigmatisation of religious minorities
日本語訳全文(UPF JAPAN 公式note)
追記
当プレスリリースに関連して、以下にUPF JAPAN公式YouTubeチャンネルにアップされている動画を添付します。本年6月と9月にスイス・ジュネーブで開催された国連人権理事会の第59回、60回会期に合わせて行われたサイドイベントの様子を収めた動画です。6月16日は当法人法務副局長・近藤徳茂と教会員の小出浩久さんが発表者として参加し、9月26日は近藤と教会員の西悦子さんが発表者として参加しました。
6月16日 国連人権理事会サイドイベント(UPF JAPAN公式YouTubeチャンネル)
9月26日 国連人権理事会サイドイベント(UPF JAPAN公式YouTubeチャンネル)