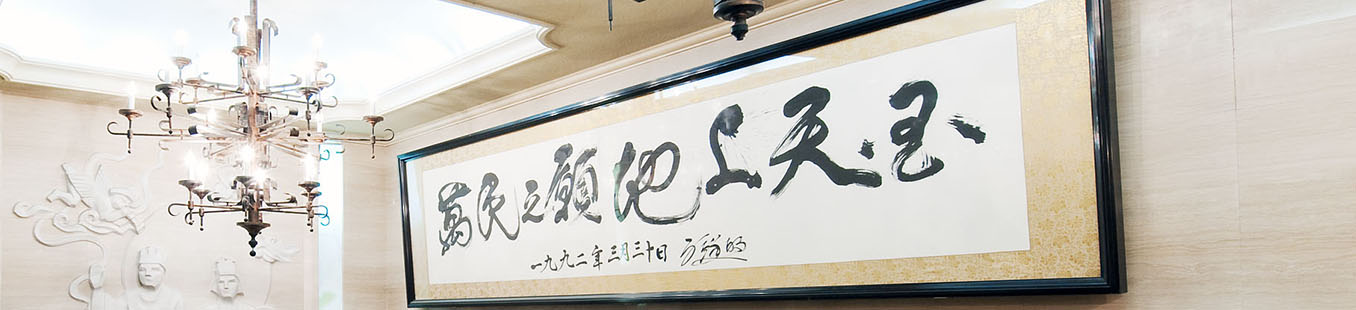ニュース
NEWS指定宗教法人の清算に係る指針案に対する意見
プレスリリース
世界平和統一家庭連合
法務局
文部科学省は「指定宗教法人の清算に係る指針案に関する意見募集の実施について」として、2025年9月6日付でパブリックコメントを募集している。
以下の通り、本指針案の内容には、信徒の人権・権利を侵害するおそれのある文言が多数含まれており、当法人の清算には法的に正当な理由がないことを踏まえて、以下のように当法人としての意見を表明する。
1.信徒の信教の自由と個人情報が守られない
指針案には次の記載がある。
「指定宗教法人側によって被害の申出が困難な状況が作り出されているような事情等から、早急な申出が困難な場合や、証拠資料の隠匿、散逸、欠損等を伴う場合が想定されることを踏まえると、まずは被害の申出を促す工夫が求められる(5頁)」
世界人権宣言、国際人権規約においては、「宗教(信教)を表明する自由」が保障されている(18条)。この「宗教を表明する自由」には、当然ながら「表明しない」自由も含まれる。法人が実際に解散される事態となれば、その社会的影響を考慮し、自らの信仰を第三者に知られたくない、すなわち信仰を有していることを一切表明したくないと望む信徒が多数存在することは容易に想像される。
日本国憲法20条に基づく信教の自由もまた、当然ながら「信仰を表明する自由」のみならず、「信仰を表明しない自由」も含まれているのである。
そして、この趣旨は、国内法である個人情報保護法(平成15年)においても、信条情報を要配慮個人情報として取り扱うことにより保障されている。
要配慮個人情報の取得や第三者提供には、原則として本人の同意が必要であり、オプトアウトによる第三者提供は認められていない(同法第2条、第27条)。
したがって、単なる関心から宗教書籍を購入する程度の行為は要配慮個人情報には該当しないが、「信徒情報」、たとえば、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、写真、所属教会、家族関係、入会の有無、礼拝参加率等の個人を特定し得る情報は典型的に要配慮個人情報に該当し、本人の同意なく第三者に提供することは許されない。
ところが、指針案では、「清算法人が保有する寄附等を裏付ける記録から判明する一定の範囲の相手方に対して、被害の申出をする意思があるか否かを個別に照会する」と記されている。この「記録から判明する相手方に対して個別に照会」については、どのようにして信者の情報を入手するのか、その手続的観点は全く示されていない。
会社法上の破産手続きでは、債権者は自ら申し出るのが原則である。本件においても、返金を請求する者は自ら意思をもって申出をするはずである。
それにもかかわらず本指針案は、清算人が潜在的債権者を掘り出すことを前提にしており、清算人の権限の逸脱とも言えるし、これは信徒情報の不当な利用を正当化する危険な仕組みである。
更に、申出をした債権者や知れている債権者への弁済がひととおり終了した時点において、清算法人の財産を帰属権利者に引き渡さないこと(以下「本件取扱い」という。)は、清算法人及び帰属権利者の財産権を侵害するものであり、憲法第29条1項に違反する。
2.債権者の対象が無制限であり、清算の終局が不明確である
本指針案には次のような記載がある。
「清算人は、被害の申出が続く蓋然性があり、被害者に対する債務の弁済を完了していないと合理的に判断できる場合は、清算法人の財産の全てを帰属権利者に引き渡すことは相当ではない。(6頁)」
「清算人において、申出をした債権者や知れている債権者への弁済がひととおり終了した時点であっても、申出をしていない被害者がなお存在し、それほど遠くない時期に申出をする蓋然性がある等、債務の弁済を終えていないと合理的に判断できる場合は、清算法人の財産につき、その時点では帰属権利者への引渡しを行わず、今後、申し出ることが予定される被害者に対する弁済に充てることの当否を検討すべきである。(7頁)」
このような記載は、被害の申出を事実上無期限に認め、清算手続の終局を著しく不明確にする。通常の会社清算であれば、公告に応じて自主的に申し出た債権者への配当で終局するのが原則である。
しかし、本指針案では、申出をしていない信徒や信徒以外の者についても、本人の同意を得ずに個人情報を取得・利用し、事実上無制限に「潜在的被害者」の掘り起こしを行うことを予定している。これでは、法人への献金は本質的にすべて違法であると決めつけ、信徒が「被害者」を名乗れば、いつでも請求が可能であるかのような制度設計になってしまう。信仰心で寄付した信者らの自由意思、信教の自由を無視して「マインドコントロール」が解けるまで、その名乗りには時間がかかるとでも言いたいのか。
すなわち、教団の資産の形成には、現役一般信者が日々の献金を通して貢献しており、特にここ数年だけでも現役信者らの信仰に基づく献金額は現在の保有資産額を上回る額となっており、彼らの資産でもあるという視点が全く欠けている。
3.特定不法行為の内容が不明確である
指針案において、何が具体的に「特定不法行為」に該当するのか明確にされていない。「特定不法行為」を「解散命令事由となった不法行為」とするが、その内容は「先祖の因縁」、「人の弱みに付け込む」といった抽象的な表現にとどまっており、客観的で具体的な行為の定義がない。
他の多くの宗教団体の宗教行為と、家庭連合の固有の「特定不法行為」の区別はなにか、示されていないし、法的根拠として極めて不明確である。家庭連合の解散理由として、宗教法人法81条1項1号の「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」とあるが、その根拠は「民法の不法行為を構成する行為が法81条1項1号にいう法令に違反する行為にあたると解したとしても、同号の文理に反しない」(最高裁令和7年3月3日決定)であるが、これは罪刑法定主義(憲法31条)に反する「法律の拡張解釈」と言わざるを得ない。しかも、家庭連合の解散理由とされた「特定不法行為」は、事実と証拠の根拠を欠くものであることから、当法人は解散命令を出した東京地裁の決定に対して事実と証拠に基づき反論している。これに対して国は全く事実と証拠による反論をしていない。
4.結論
以上のとおり、本指針案には、
① 信徒情報を当然のように利用する前提に立ち、信教の自由(表明しない自由)および個人情報保護法の趣旨に反している。更に、清算法人及び帰属権利者の財産権を侵害するものであり、憲法第29条1項に違反する。
② 被害申出を無期限に認め、清算手続の終局を不明確にしていること。その目的は被害者の掘り起こしであり、清算人の権限の逸脱であり、それによる国による特定の宗教の自由への侵害であり、政教分離違反である。
③ 特定不法行為の内容が不明確であること。解散命令は何ら事実と証拠に基づかない証拠裁判主義に反する決定である。そのような違法な決定に基づいた清算手続きは許されない。
という三つの重大な問題を抱えている。
したがって、本指針案は、憲法20条、個人情報保護法、さらに国際人権規約18条の趣旨に照らしても、信徒の人権に十分な配慮を欠くものであり、このまま策定・実施することは許されない。
以上