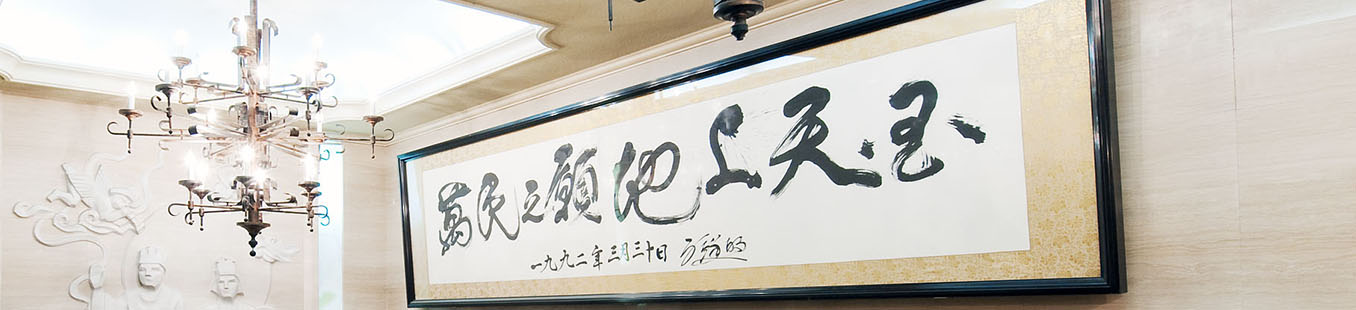ニュース
NEWS解散命令裁判に関わる和解・示談事案の一部を公開します
プレスリリース
世界平和統一家庭連合
令和7年3月25日付東京地裁決定(鈴木謙也裁判長、以下「地裁決定」)は、当法人に関する民事訴訟の確定判決だけでなく、①訴訟上の和解、②裁判外の示談案件をも根拠にして当法人の不法行為を推測し、大幅に被害額を水増しすることで殊更に悪質性を強調して解散命令を下しました。
この不法行為被害の水増しは、コンプライアンス宣言後の2010年以降について顕著に表れています。即ち、同年以降の献金に関する民事判決はわずか2件にとどまりますが、地裁決定はこれに加えて、①訴訟上の和解8件9名(2010年以降の献金を一部でも含むものは対象に入れる)と、裁判外の示談167名(〃)を挙げて、2010年以降も「なお看過できない程度の規模の被害が生じているということができる」と判示しました。ところが、この地裁決定の判断は、文部科学省が提出した証拠を精査せず(あるいは全く読まずに)、和解・示談事案を十把一絡げにして、一方的に当法人に不法行為があったと推測するものでした。
抗告審では、コンプライアンス宣言後の和解案件1つ1つの中身に立ち入り、各事案がどのような事実関係で、どうして和解に至ったのかにつき、証拠を摘示しながら詳述することにより地裁決定が行った推測の誤りを詳細に論証しました。たとえば、訴訟上の和解案件には、被害申告者側による証拠捏造が立証された当法人の全面勝訴案件や、そもそも裁判で不法行為が一切主張されていない案件等が含まれ、裁判外の示談案件でも、被害申告者、代理人弁護士又は文科省による虚偽証拠捏造の事実が明らかになっているものもあります。上記の問題点は、文科省及び当法人が一審で提出した主張書面及び証拠を“読みさえすれば”、明らかなことでした。地裁裁判官においては、証拠をまともに読みもせず、表面的な数字(被害額)だけを追い求めることで実にいい加減な判断を下したのでした。
また、今回の反論により、地裁決定が「想定」した「顕在化していない被害の存在」が単なる空論であることもより一層明白となっています。本プレスリリースでは、和解・示談事案に関する具体的な反論(各論)の一部を添付の文書にて紹介しますので、ぜひご参照ください。
和解・示談事例各論要旨(PDF)
和解・示談事例各論の解説動画(2025.5.13更新)